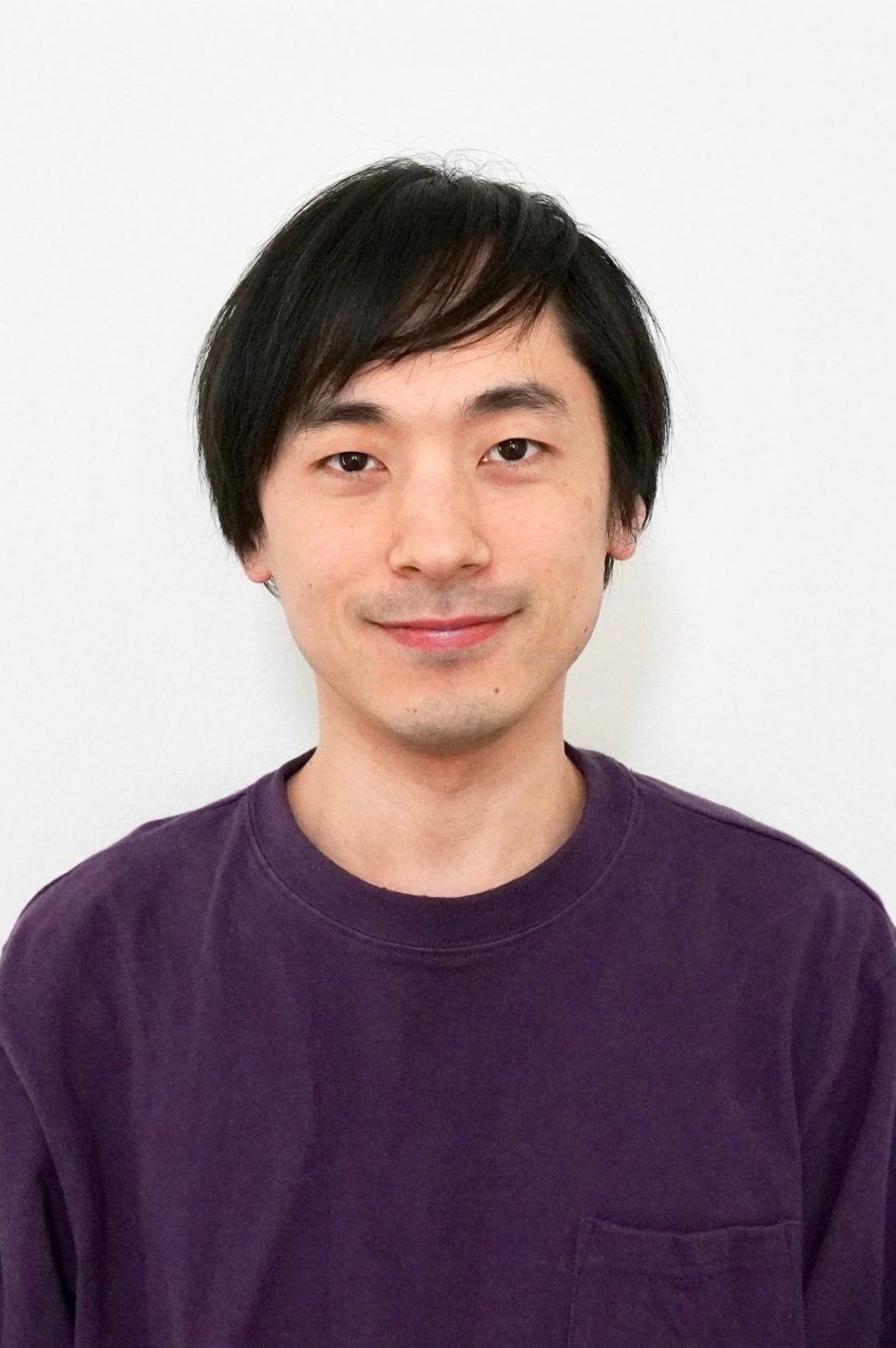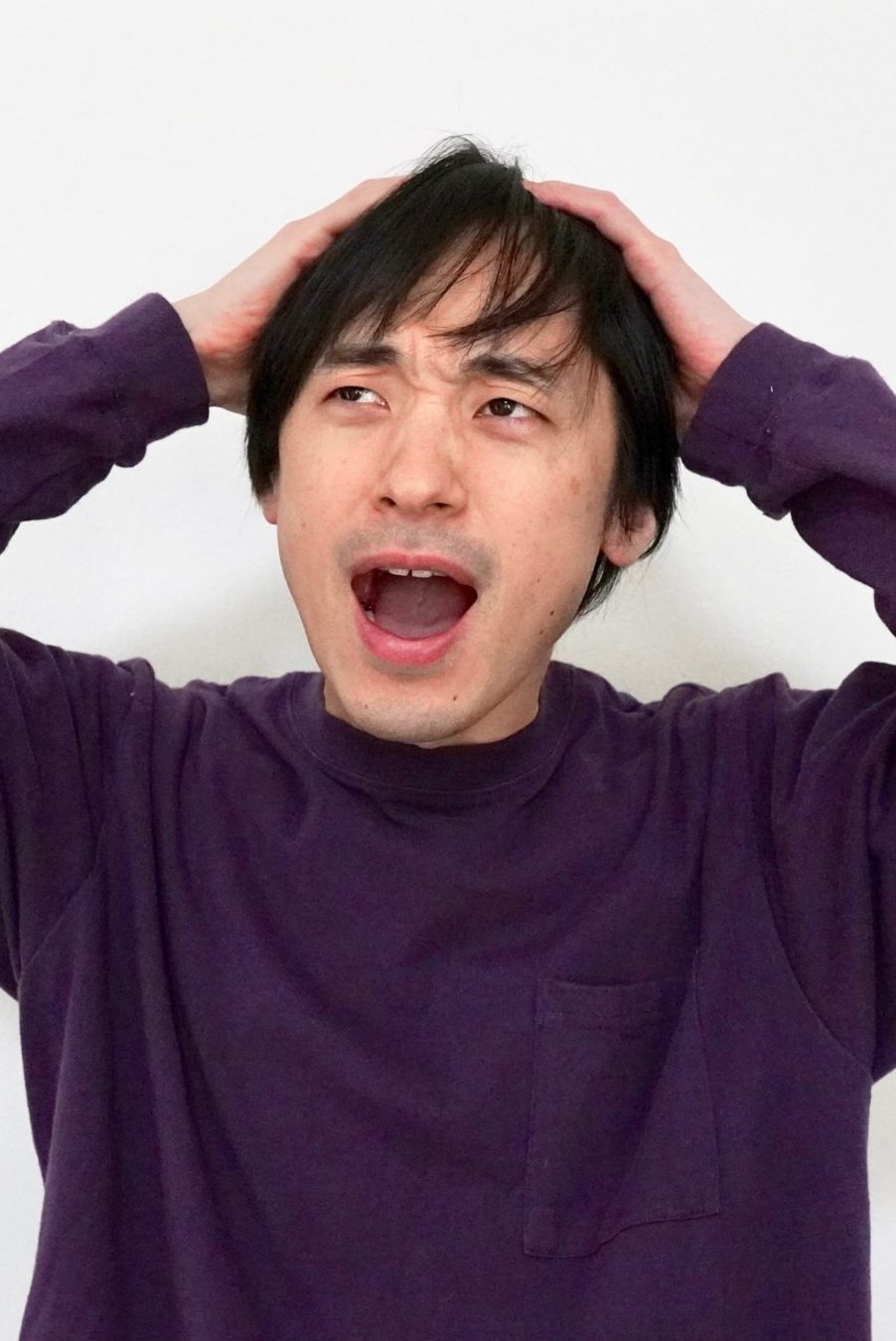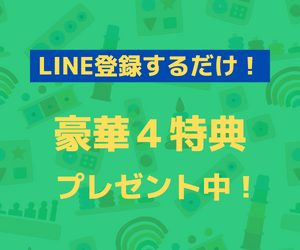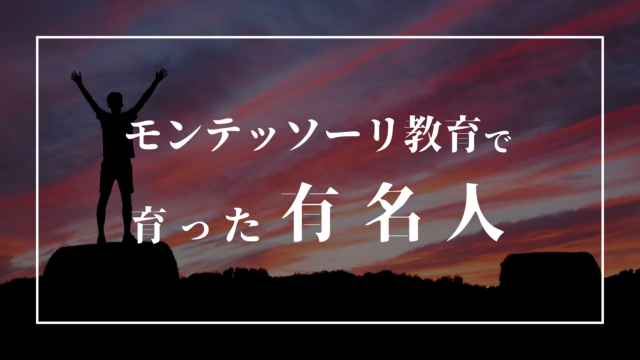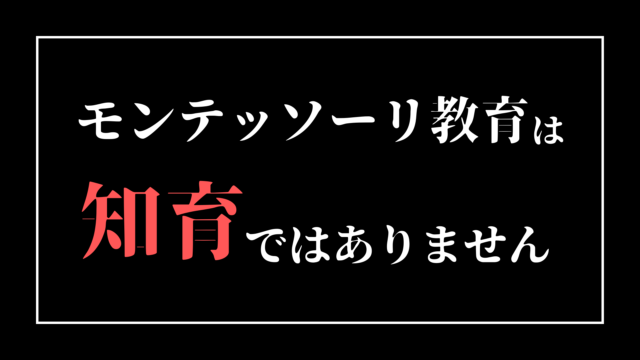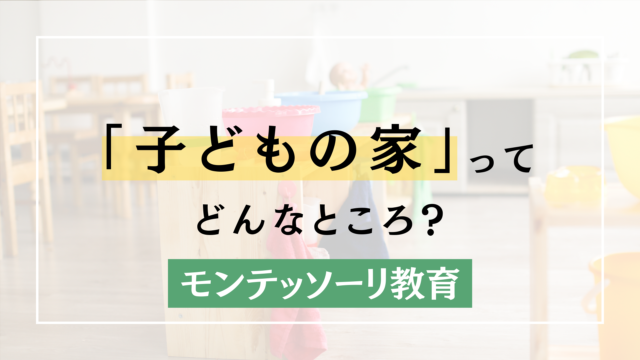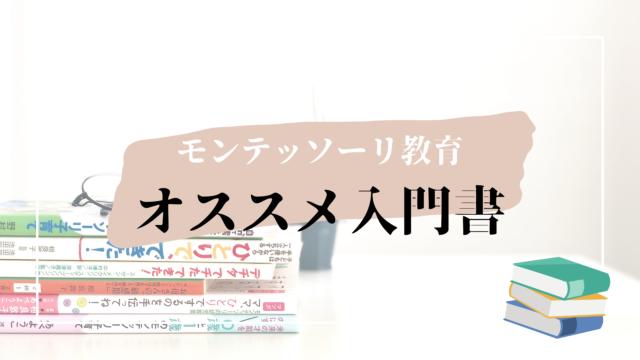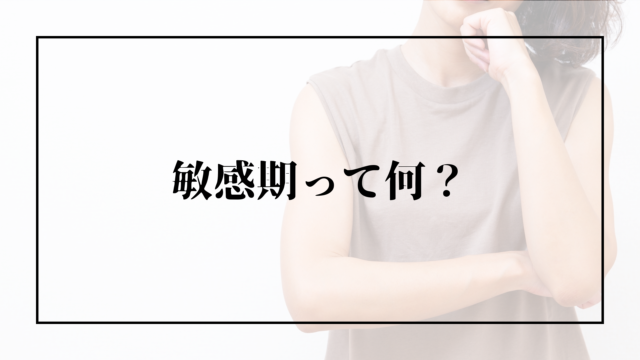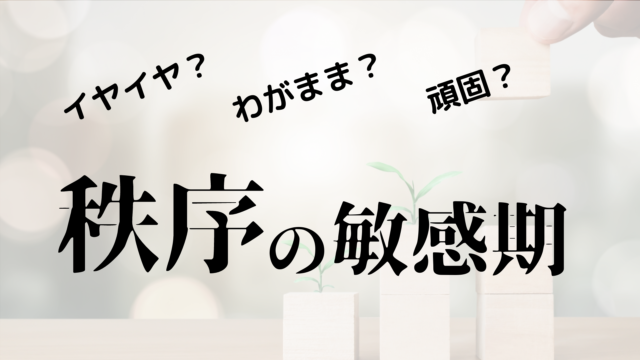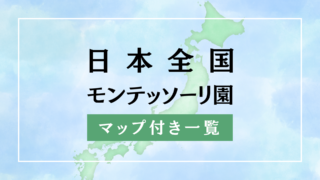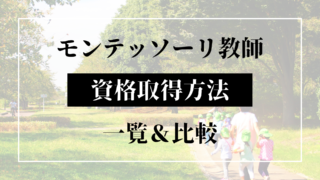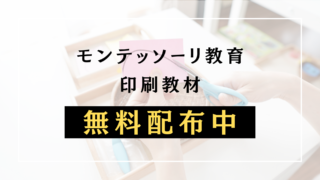当サイトでは、国際資格を持つモンテッソーリアンまりこが、モンテッソーリ教育についてできるだけわかりやすい言葉を使って解説しています。
モンテッソーリ教育の園に向き不向きはあるのでしょうか?
モンテッソーリアンまりこが、実際に園で働いていたときの経験を交えつつ解説します
子どもに向き不向きはない
モンテッソーリ教育では、子どもは自分がやる活動を自分で選択できます。
つまり、子どもはやりたいことに取り組めるということです。
モンテッソーリ教育の園には、子どもの色々な「やりたい」にも対応できる、様々な活動があります。
つまり、どんな子でも、自分の「やりたい」を見つけられる環境があるんです。
外で遊ぶのが大好きな子の場合
モンテッソーリ教育というと、屋内でやる手先の活動や知的な活動のイメージが強い方も多いかと思いますが、体全体を使うこともとても大切にしています。
なぜなら0〜6歳というのは体を動かすのが楽しい時期だからです(運動の敏感期)。
園によってどれくらいの時間取り入れているか、園庭があるかないかなどに左右されますが、外で遊ぶ時間は必ずあります。
また、わたしの経験上では、はじめは体全体を使う活動が好きな子も、だんだんと手先の活動に興味を持つようになり、だいたい4歳くらいで体全体の活動から、手先の活動や知的好奇心を満たしてくれる活動へ興味が変わっていくことが多いです。

外で遊ぶ時間もある。年齢が高くなってくると自然と屋内の活動もやるようになる。
落ち着きがない子の場合
「落ち着きがない」=「本当にやりたいことを見つけられていない」というようにモンテッソーリ教育では考えています。
「落ち着きがない」というのはその子の本質ではなく、やりたいことがない環境が落ち着きをなくさせてしまっている場合が多いんです。
そして、やりたいことを見つけるのがモンテッソーリアンの仕事。
子どもがどんなことに興味があるのか、どんなことをやりたがっているのか見極めて、子どもがやりたいことをできる環境を用意します。
時間がかかることがあるかもしれないですが、その環境の中で子ども自身が本当にやりたいことを見つけられれば、落ち着いて活動できるようになってきます。
落ち着きがない子も、やりたいことが見つかれば落ち着いてくる。
ただし、やりたいことを環境に用意するのが先生の仕事なので、園の先生の質も大事。
やりたいことを自分で選べない子の場合
正直にいって、やりたいことを自分で選べない=自己選択できない子は、なれるのにすごく時間がかかります。
ですが、このまま自己選択できないままでいいのでしょうか?
自己選択できない理由はさまざまですが、ほとんどが今まで自己選択する機会が少なかったからです。
モンテッソーリ教育では1日の中で自己選択しなくてはらない場面が何度もあります。
最初はなれなくて大変かもしれませんし、時間もかかるかもしれませんが、だんだんと自己選択できるようになっていきます。
自己選択できない子は、なじむのに時間がかかるかもしれません。
ただ、自己選択できるようになるという意味ではむいている。
向き不向きがあるのは大人のほう?

「〇〇をやらせたい」、「〇〇になってほしい」、「元気で活発であってほしい」、「大きな声で返事をしてほしい」、子どもに対していろいろな希望や願望を持つことは親なら誰でもありますよね。
それ自体は素晴らしいことですが、その願望を子どもに押し付けてしまうことはモンテッソーリ教育の理念に反してしまいます。
子ども自身の「こうなりたい」「やりたい」というのを引き出すのがモンテッソーリ教育なので、親にかぎらず誰かの「こうさせたい」というのは正反対の考え方なんですね。
モンテッソーリアンは親の「こうさせたい」より子どもの「こうしたい」をつねに重要視します。
「こうさせたい」という思いが強い親御さんは、園が思うように対応してくれないことで不信感をもってしまうかもしれません。
どうやって自宅でモンテッソーリ教育を取り入れるの?
それなら「子育ての学校 ~おうちではじめるモンテッソーリ教育~」
基本的にモンテッソーリ教育はどんな子どもにも向いている。
手先の活動などじっと活動しているイメージがあるかもしれませんが、外遊びもしっかりできる。
落ち着きがない子や自分のやりたいことを選べない子は、なじむまでに時間がかかるかもしれないが、むしろそういう子にこそモンテッソーリ教育を受けてほしい。
子どもに「こうさせたい」という思いが強い親御さんには向いていないかもしれない。
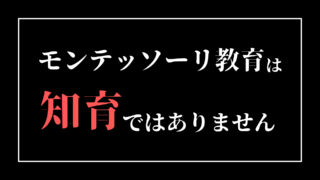
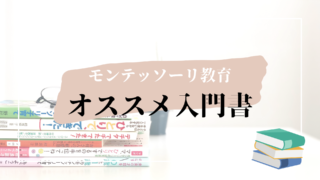

子育ての学校であなたも子育てのプロになろう!
⚫︎ 発達の知識を学ぶ
⚫︎ 関わりを学ぶ
⚫︎ おもちゃや活動を学ぶ
⚫︎ 環境づくりを学ぶ
⚫︎ 実践を学ぶ
⚫︎ 同じ教育方針の仲間をつくる
知らないで子育てするなんてもったいない!
今すぐ学んで、子どもの成長をぐんぐん手助けしましょう!