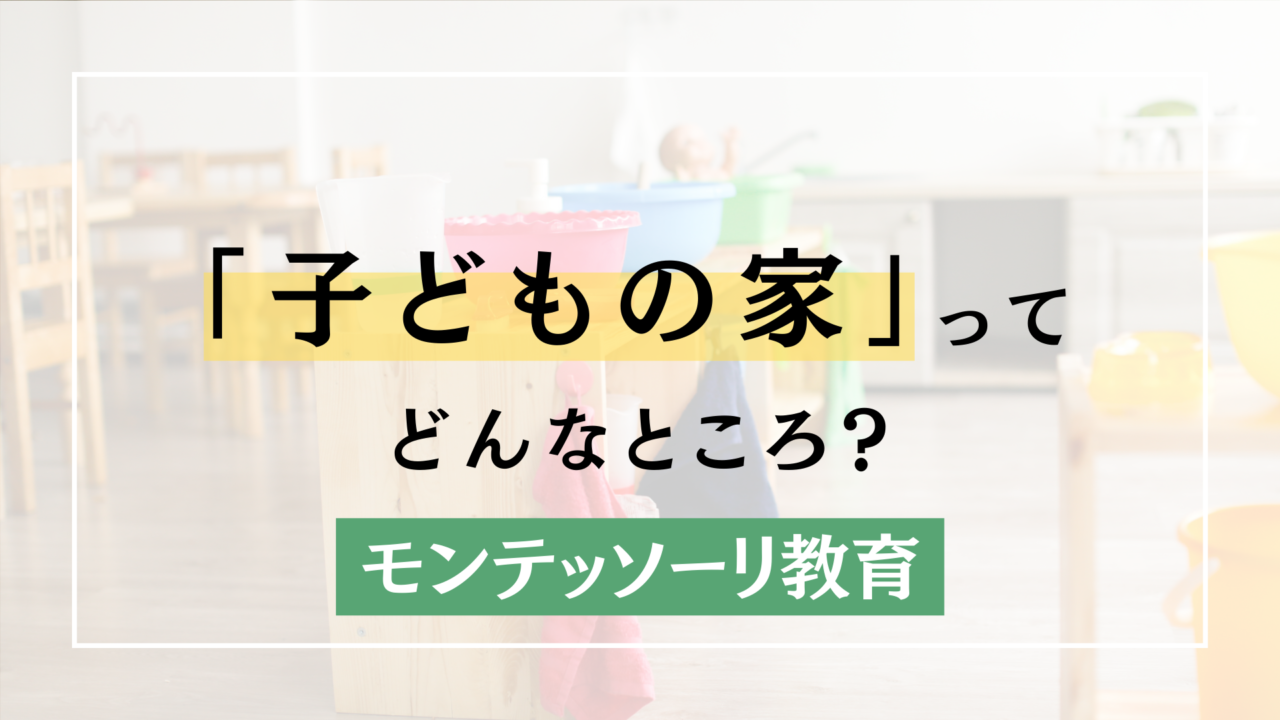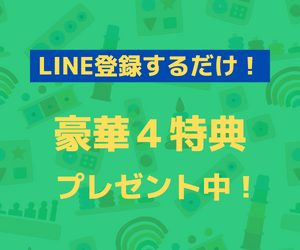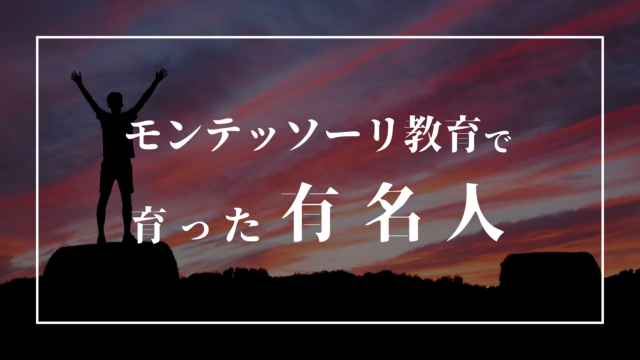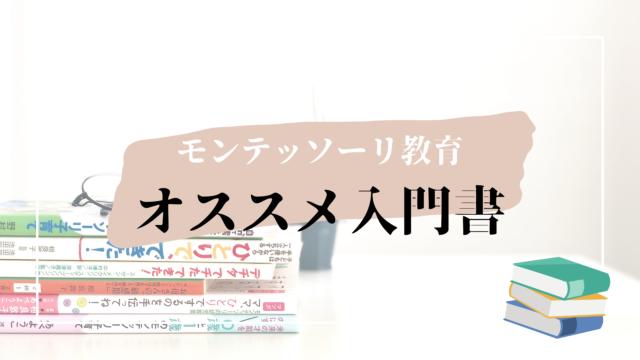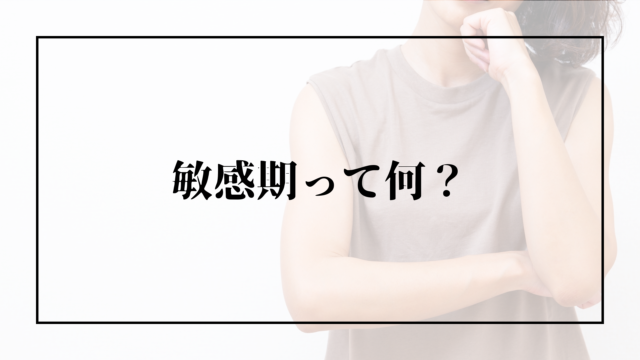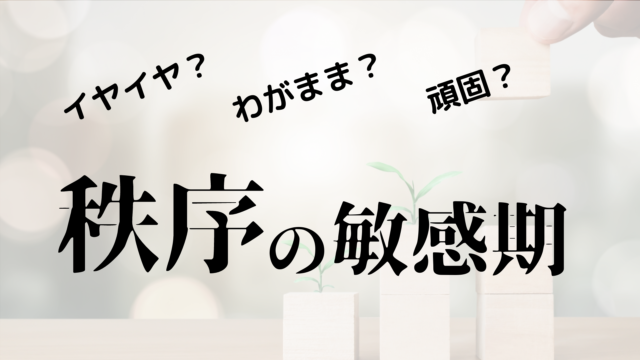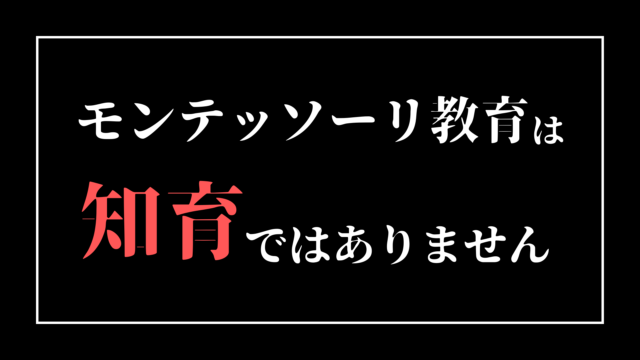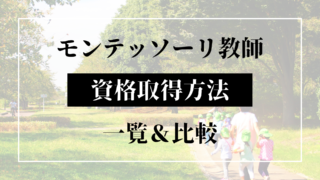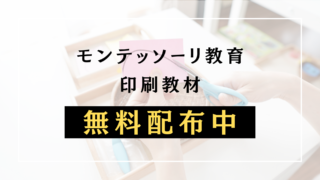当サイトでは、国際資格を持つモンテッソーリアンまりこ監修のもと、モンテッソーリ教育についてできるだけわかりやすい言葉を使って解説しています。
モンテッソーリ教育に触れたことがない人にもわかりやすく「子どもの家」について解説します!
映画を見る前にも「子どもの家」がどんなところか予備知識があると、より楽しめると思います!
子どもの家とは
「子どもの家」とは
モンテッソーリ教育を実践している保育施設の総称
「子供の家」、「子どもの家」、「こどもの家」、「Childrens’s House」、「Casa dei Bambini(イタリア語)」など表記は様々です。
子どもの家の特徴

子どものための生活空間がある
わたしたちが住んでいる家は、大人のために設計された生活空間です。
キッチンや洗面台、トイレなど、生活に必要なものはすべて大人が使いやすい高さ、サイズになっていますよね。
一方、子どもの家は、子どもが生活しやすいように設計された子どものための空間です。
子どもが使いやすい高さの机、イス、トイレ、流し、簡単な料理ができる作業台などが用意されています。
また、ほうき、ぞうきん、バケツ、ピッチャー、料理道具、ハサミ、アイロンなど、様々な道具が子どもが扱いやすいサイズで用意されています。
子どもサイズにするだけで、子どもが生活に参加するハードルがぐっと下がります!
子どものための活動・教具・教材がある
「日常」「感覚」「言語」「数」「文化」「芸術」などの分野ごとに様々なモンテッソーリ教育の活動・教具・教材が用意されています。
子どものどんな興味にも対応できることで、子どもは「やりたい」という気持ちを満たし、「できた」という経験を繰り返すことで、心と身体を育てていきます。
モンテッソーリ教育に精通した先生がいる
生活空間や教具などモンテッソーリ教育的な環境だけがあっても、モンテッソーリ教育はできません。
そこには必ずモンテッソーリ教育に精通した先生がいます。
先生は子どもに教える存在ではなく、子どもと環境、子どもと活動や教具の橋渡しをする存在として、子どもを援助します。
異年齢が同じクラスにいる(縦割り)
年少者は年長者を見て学び、年長者は年少者の見本となったり、ときには年少者に手を貸したりすることが学びになります。
実際の社会でも年齢が違う人が一緒に働いていますよね。
子どもの家も同じです。年齢の異なる子ども同士が関わりあい、社会性を身に着けていきます。
子どもの家での子どもたちの様子

自立して生活する
子どもの家には子どものための生活空間があります。
そんな中だからこそ、子どもが自立して生活する姿を見ることができます。
自分でトイレに行くなどはもちろん、料理をする姿や配膳をする姿、掃除をしたり、アイロンがけだったりを、大人に言われてやるのではなく、自分たちの意思でやっています。
先生どこにいるの?って思ってしまうほどです。
自分で活動を選ぶ
子どもの家には何百もの活動がありますが、子どものはその中から自分で活動を選びます。
モンテッソーリ教育では自己選択することをとても大切にしているんです。
色々解説しましたが、百聞は一見にしかずです。
映画「モンテッソーリ 子どもの家」の映像が少し公開されているので、ぜひ見てみてください!
日本における子どもの家

「こどもの家」を名乗るために条件が定められているわけではないので、様々な形の子どもの家があります。
認可・認可外問わず、モンテッソーリ教育を取り入れている保育園や保育施設が「子どもの家」という名前を使っている場合があります。幼稚園
モンテッソーリ教育を取り入れている幼稚園が「子どもの家」という名前を使っている場合もあります。教室
週に数回、1回数時間だけモンテッソーリ教育を受けられるようなモンテッソーリ教育のお教室が「子どもの家」という名前を使っている場合もあります。
モンテッソーリ教育とは関係ない施設
児童養護施設など、モンテッソーリ教育とは関係なくても、「子どもの家」という名称の施設もあります。
こちらはモンテッソーリ教育を取り入れている教室の様子です。
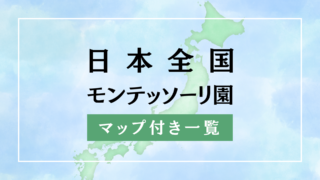
まとめ

これで映画の内容に集中して楽しめそうです!
映画『モンテッソーリ子どもの家』は2月19日から全国公開!
モンテッソーリをあまり知らないという方からモンテッソーリ教師まで、ぜひたくさんの人に見てほしいです。

子育ての学校であなたも子育てのプロになろう!
⚫︎ 発達の知識を学ぶ
⚫︎ 関わりを学ぶ
⚫︎ おもちゃや活動を学ぶ
⚫︎ 環境づくりを学ぶ
⚫︎ 実践を学ぶ
⚫︎ 同じ教育方針の仲間をつくる
知らないで子育てするなんてもったいない!
今すぐ学んで、子どもの成長をぐんぐん手助けしましょう!